編集者
2025.10.15
漫画の制作フローを各工程別に編集者に質問してみた!
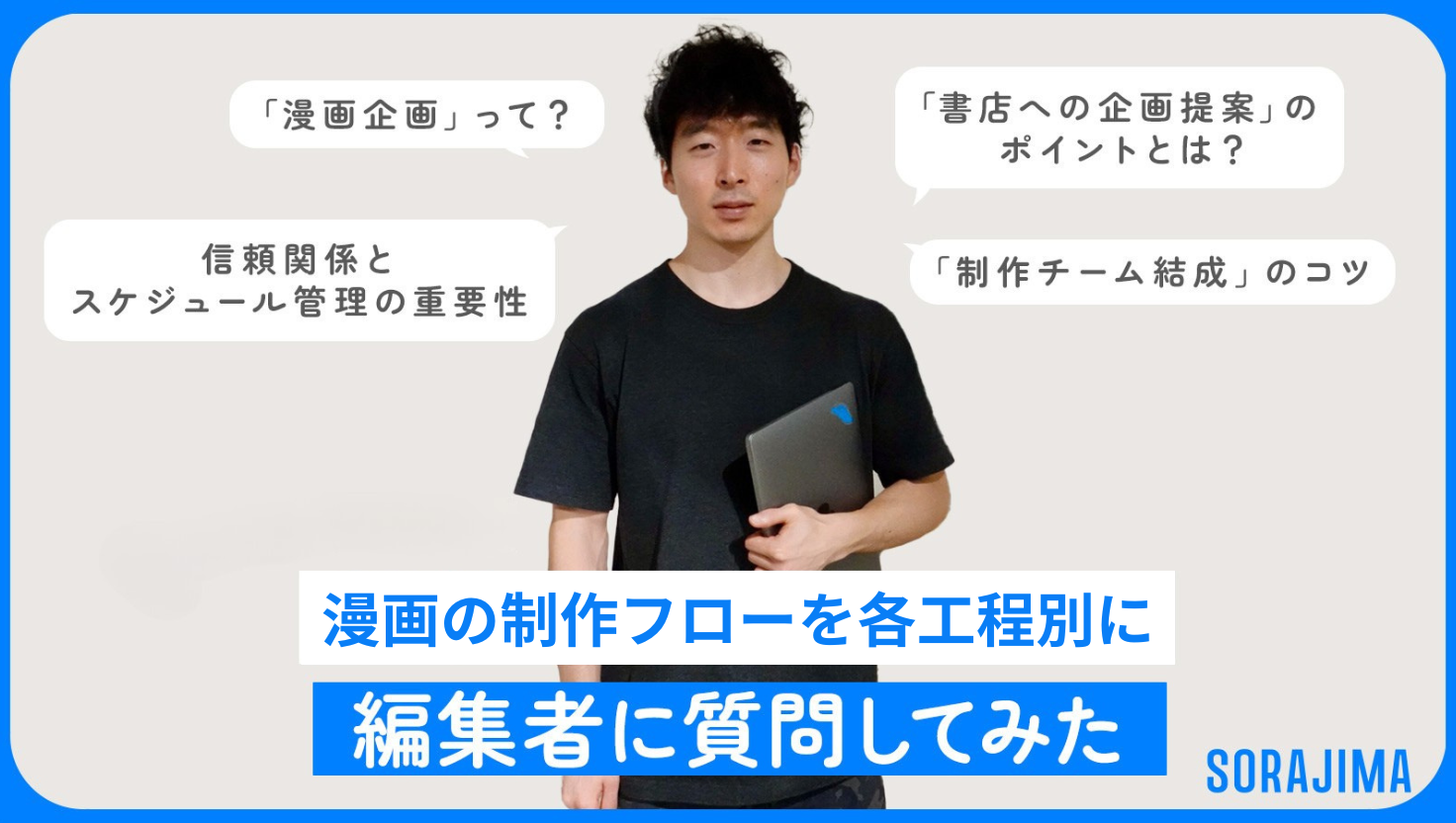
はじめに
漫画編集者と聞くと、「作家が作った原稿をチェックして、締め切りを管理するだけ」というイメージを抱いていませんか?
実は、漫画編集者の仕事は企画立案から制作、プロモーションまで多岐にわたります。
本記事では、ソラジマで編集チーム長として活躍している池田啓真さん(担当作品:『天才暗殺者、2度目の人生はアカデミーから』など)に「フロー工程別」に仕事内容を徹底インタビュー。
クリエイターとの関わり方、スケジュール管理のコツ、ヒット作を生み出すための工夫などをリアルに解説します。
また、ソラジマの編集者ならではのやりがいや仕事の魅力、今後の目標についても語っていただきました。
【この記事はこんな人におすすめ】 |
|---|
目次
他では味わえない自由度がある、ソラジマの編集者
各工程を解説していただく前に、ソラジマの環境の特徴を教えてください。
一番は「裁量」だと思います。ソラジマでは未経験の編集者でも大きな裁量を任されます。
他社では、入社後はしばらく研修期間として過ごし、その後に配属が決まるケースが多いそうです。さらに配属後も連載担当編集者になるまでには1~2年ほどかかるのが一般的だと聞きました。
一方ソラジマでは、入社直後から作品を担当することも珍しくありません。しかもチームではなく一人で企画から脚本・仕上げまで担うので、裁量は格段に大きくなります。
ソラジマの編集者は「裁量が大きい」とのことですが、より具体的に編集者として関われる裁量の範囲を教えてください。
どんな企画で攻めていくか、そしてその企画を進める上でどんなクリエイターさんと一緒にチームを組むか。このチームビルディングの部分は、完全に編集者に委ねられています。
編集部の中では「市場で売れるのは難しい」と判断された企画であっても、編集者が「この企画は売れる」という理由をきちんと説明できるのであれば自由に進行できます。
ただし、実際に連載するためには社内の審査に通らなければなりません。企画としてチャレンジするのは自由ですが、実際に制作を継続できるかどうかはまた別です。
なぜ、ソラジマでは未経験であっても入社直後から全工程を担当できるのでしょうか?
理由の1つは、会社のカルチャーにあります。
ソラジマには「Why No Feedback?」というカルチャーが根付いており、社員同士がフラットに意見を言い合う機会がとても多いんです。
このカルチャーのおかげで風通しがよく、新入社員でもベテラン編集者にアドバイスやノウハウを気軽に聞けます。
だから未経験でもキャッチアップが早く、入社直後でも活躍できるんです。
なるほど。ほかにも理由はありますか?
あとは、やっぱりWebtoonに特化している点も大きいかと。日本でWebtoonを本格的に制作している企業やクリエイターさんはヨコ読み漫画に比べるとまだ少ないです。
Webtoonという新しい漫画のスタイルだからこそ、ノウハウもまだ発展の途上です。これからいろいろな多様性を創っていく状態だと思います。
そのため、まったくの未経験の編集者が入ったとしても、先人たちの積み上げてきたものをキャッチアップする時間がヨコ読み漫画よりも少なく済みます。
それも理由の一つではないでしょうか。
「漫画企画」――日々の市場分析が要となる

では、編集者の仕事をフローごとに詳しくお聞きします。一つめの工程である「漫画企画」を立ち上げる際、何から始めますか?
企画の立ち上げ方は編集者によってさまざまですが、大きく分けると2つあります。
これはソラジマやWebtoonに限らず、漫画業界全体の基本的な方法です。一つ目は、話し合いを通してゼロから作家さんに企画を作っていただくパターン。もう一つは、編集者が企画の種を作り、それを作家さんと一緒に広げていくパターンです。
漫画企画の工程の中に「Webtoonを分析」とありますが、具体的にどんなことを行うのでしょうか?
まずは市場の分析からスタートします。
編集者であれば、担当しているジャンルの中でも主要なプラットフォームを日常的にチェックしますよね。

たとえば僕の場合は、LINEマンガやピッコマなどで「どんな新作がでているか」「どうやって新作がプッシュされているか」「その新作がどのくらい伸びているか」「既存のヒット作の売上はどう変動しているか」を毎日追っています。
こうした日々の記録が分析の基盤になるんです。
編集者が企画を作るとき、“ヒットする作品を作る”ことが前提にあります。
そのために、毎日の市場分析で「今の市場でヒットするために必要なもの」「今読者さんが求めている感情の動き」を大きいものから小さいものまで見つけて、言語化することが大切です。
そして、言語化したものを作家さんと一緒に作品に落とし込みます。今の読者のニーズに沿うかどうか解像度を高めていくイメージですね。
日々の「データ分析」が大切と話していただきましたが、数字には表れない「感覚」も大切ではないでしょうか?
コンテンツって正解がない世界なので、どちらも重要だと考えています。
定性的な感覚も大切ですし、数字として表れるデータも大切です。
ヒットを狙う上で「データ分析」と「感覚」のバランスはどう取っていますか?
僕の中のバランスとしては、数字は「答え」に近いですね。
Webtoonは毎週新作が出ていて、リリース直後はview数もいいね数もすぐには集まらず、好調か不調かを判断できるだけの「数字」は分からないんです。
いつも数字からはまだ売れ行きが好調か不調かを判断できない段階で新作を読み、「これは初日どれぐらい売れるんだろう」「1週間後はどれぐらい売れるんだろう」などなど予想を立てています。
そして、実際の数字である「定量的な結果」と自分の感覚である「定性的な予想」がどれだけ離れているかをすり合わせて「答え合わせ」をしています。
ただ、一番重視しているのはやはり自分の感覚です。数字は一つの指標として参考にしつつ、「この作品はどれだけ読者に受け入れられそうか」を解像度高くイメージできることが理想です。
「企画書会議」とは、どのようなものでしょうか?

企画書会議は週1〜2回ほど行っています。ソラジマではジャンルごとに4〜5人の編集者でチームを組んでいて、そのチームごとに会議を開きます。
入社時期も経歴も関係なく全員がお互いの企画書についてフラットに忖度せずフィードバックし、ブラッシュアップしていくんです。
それ以外にも、ソラジマではSlack上でいつでも誰にでもフィードバックをもらえます。チーム外のメンバーから企画書に意見をもらうことも日常的です。
「書店への企画提案」――作品がヒットするビジョンを見せる

プラットフォームや書店に企画を提案する際、どんなポイントを意識していますか?
まず企画を考えるときから、そのプラットフォームでしっかりと売れることを意識します。
さらに、普段そのプラットフォームを利用していない人が読んでも、しっかり没入できるものにしたいなとも思っています。
そのために、自分の企画と類似する作品はすべてチェック。ヒットしている作品も、そうでない作品も読み込み、「ヒットの分かれ目ができている理由」をできる限り具体的に言語化します。
もちろん、コンテンツには言語化できない領域もたくさんありますが、プラットフォームに提案する際には「なぜ企画が売れると思うのか」という戦略をある程度説明できたほうがいいですから。
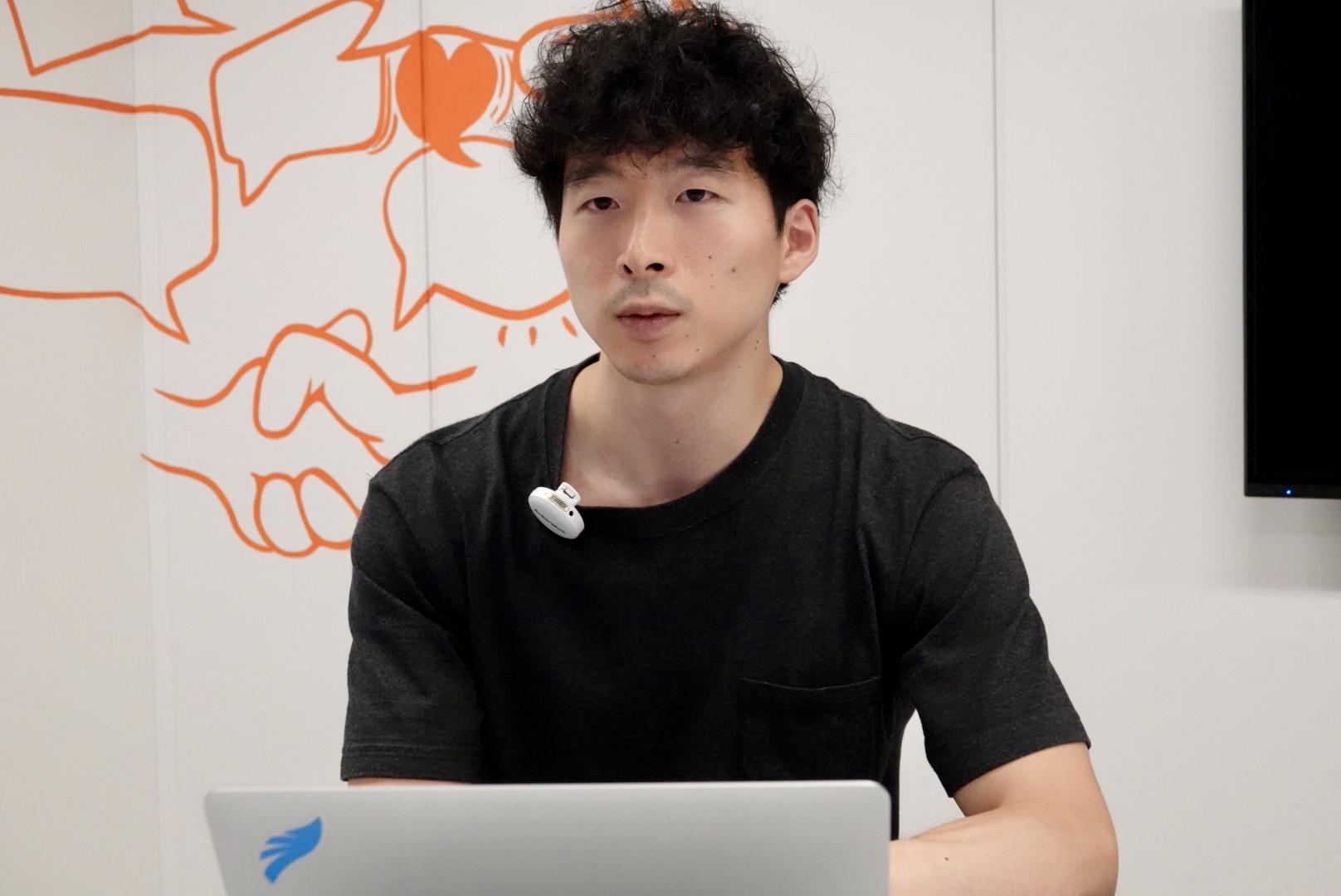
日々の市場分析で得たものと、企画が売れる理論を組み合わせて提案するのですか?
そうですね。あとは、プラットフォーム外の読者にも読んでもらえる理由を伝えることも大切です。
今は「バズり」の影響がとても大きいので、この作品がどうバズり、どう拡散していくのかというビジョンも示せるといいと思います。
きちんと今後のビジョンまでお話するんですね。
はい。やはりアニメ化を目指したいので、作品のオリジナリティや今のWebtoonの市場でヒットする根拠、さらにより大きくヒットする要素は説明できるようにしています。
「制作チーム結成」――作品の運命を決める仲間探し

Webtoonの制作が決まったら制作チームを結成しますよね。チームを組むクリエイターさんはどのように探すのでしょうか?
Webtoonは、企画・脚本・ネーム・線画・着彩・仕上げと細かく工程が分かれているので、各工程でクリエイターさんの探し方も変わってきます。
まずは物語の産みの親、原作者さんを探すことから始まります。
原作者さんの探し方は主に二つあります。一つ目はソラジマにクリエイター登録していただいている方にコンペのお声掛けをしたり、場合によっては公募を行わせていただいたりする方法です。
もう一つは、商業での実績がある方や商業デビューしていないけれどコンテストや投稿サイトなど、面白い作品を発表している方を探し、SNSを通じてお声掛けする方法です。
他の工程もこの二つの方法でクリエイターさんを探すことが多いです。線画以降は制作スタジオにお願いすることもあります。
クリエイターさんを決定する基準はありますか?
どの工程も企画との相性が一番大きいですね。
例えば線画以降であれば、今の市場のニーズにバッチリ合う形で攻めたいときは、そのニーズに沿った絵柄に寄せられるかどうかを注視します。
一方で、あえて今の市場にはない絵柄で挑戦するときなどは、オリジナリティの強いクリエイターさんを探すなど、諸々の作品戦略に沿って判断基準を定めています。
脚本家さんは何を基準に選んでいますか?
脚本家さんや原案者さんは、Webtoonのテンポ感やWebtoon読者が求める感情体験に応えていただけるか等が重要なポイントです。
ただこれも編集の戦略次第です。どんな戦略で、どんなふうに作品を読者さまに届けたいのかによって、重視するポイントも当然変わってきます。
ネーム作家さんの場合も同様で、Webtoonはヨコ読み漫画と少しコマ割りなど毛色が変わってくるので、ヒットしている作品のネームの切り方や法則など抑えておきたいポイントが多いんです。その部分をしっかりチューニングしていただけるかどうかが選定の大きな基準になりますね。
やはり、ヨコ読みとタテ読みの違いやWebtoonならではの表現方法を理解した上でクリエイターさんを選ぶことが重要なのですね。そうしたノウハウは、入社後に培っているのでしょうか。
基本的にはそうだと思います。入社前からWebtoonをかなり読み込んでいたり、分析していたりする人もいますが、入社後に大きく成長する人がほとんどです。
編集者は日々作品を分析して言語化し、他の編集者と意見をぶつけ合っています。そんなやりとりを通して「Webtoonとして大事なことは何か」を学んでおり、大きな成長につながっていると思います。
「制作」――信頼関係とスケジュール管理が重要

制作チームを結成したあと、クリエイターさんとはどのように関係を築いていくのでしょうか。
まずは何より、信頼関係を築くことが大切です。
社会生活ではコミュニケーションを通して、お互いを理解・信頼し合うことがとても大切だと思います。編集者とクリエイターも同じです。
クリエイターさんとは密に関わる分、お互いの意向がぶつかることも珍しくありません。そのため、作品にとってベストな形を模索できるよう、フラットにデイスカッションできる関係性やお互いの意見をリスペクトできる関係性を構築しておくことが重要です。
編集者としてスケジュール管理や品質チェックで特に気をつけていることを教えてください。
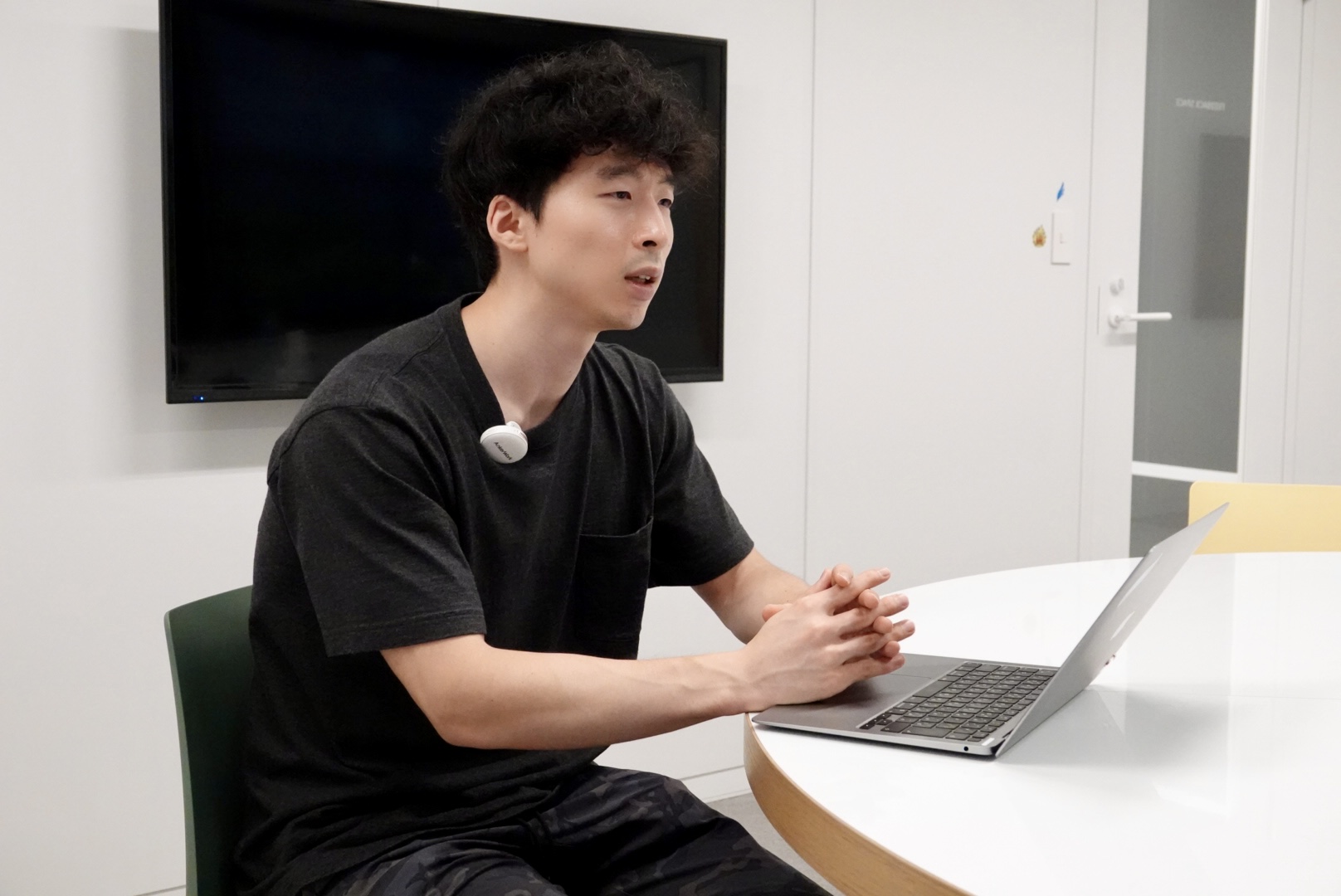
品質チェックは、「とにかく丁寧に見ること」。これが第一で、次に意識するのは「目指すヒット規模と戦略に届いているか」です。
脚本・ネームのコマ割り・線画・着彩などすべてが「今の市場でヒットする形になっているか?」と精査するんです。
同じジャンルでヒットしている作品と担当作品を照らし合わせ、線画ならコマ単位で延々と見比べますし、着彩もネームも同様にひたすら細かく照らし合わせて「何が足りていないのか」そして、「何が本作の強みになっているのか」を追求します。
なるほど。スケジュール管理はどんな点に気をつけていますか?
Webtoonには多くのクリエイターさんが関わっており、リレー形式で作業を進めています。もし一人の仕事の手が止まると、後工程のクリエイターさんの仕事や生活に影響が出てしまうんです。
だから、スケジュール管理はとてもシビアに取り組んでいます。
急なご病気や家庭の事情など不足の事態はありますが、基本的には後工程のクリエイターさんに仕事の空きが出ないよう、事前にスケジュールを把握して円滑に進められるような納期を設定するよう努力をしています。
ただ、クリエイターさんによってはとてもこだわりを込めていただいている方もいるので、そこで納期が伸びてしまうこともあるんです。
もちろん納期は大切ですが、そのこだわりがクリエイターさんのモチベーションに繋がっている部分もあるので、うまく先回りをしてスケジュールを立てておくことが必要です。
スケジュール調整も、クリエイターさんと関係性を築いておくことが大事になりそうですね。
そうですね。普段からしっかりコミュニケーションを取れていれば、クリエイターさんも言いにくいことをちゃんと相談してくれると思うんです。
だからこそ、事前に作業しやすいスケジュールを組んだり、必要があれば柔軟に調整したりできるようになります。
プレッシャーよりも、「好き」が勝る仕事
ヒット作を出すことへのプレッシャーはありますか?
もちろんあります。まず、ソラジマはスタートアップ企業なので、資金がいくらでもあるわけではありません。
「自分も何か成果を出して貢献しなきゃ」とプレッシャーを感じています。
あとはシンプルに、自分の編集者としてのキャリアを築く中で「ヒット作を出したい」という気持ちもありますね。
ほかにも、関わってくれているクリエイターさんの存在も大きいです。
作品がヒットしなければ、制作継続が難しくなり、クリエイターさんの利益に繋がりません。ご尽力いただいているクリエイターさんに還元するためにもヒットを出したいという想いがあります。

そのプレッシャーをどう乗り越えていますか?
僕の場合はもう、「絶対にヒットを出すんだ」という気概と、「好きでこの仕事をしている」という部分が大きいかと思います。
一緒に脚本やネームを作ったり、クリエイターの皆さんにご尽力いただいて作品が素敵に仕上がったり……。そんな瞬間が楽しくて、プレッシャーを忘れている時間が多いかもしれないですね。
あとソラジマは、フィードバックカルチャーがあったり、年4回の合宿があったりと編集者同士のコミュニケーションがとても密です。
同じようにプレッシャーを抱えている仲間と支え合いながら頑張っていける環境があることも大きいと思います。
ソラジマにはもう一つ、BAP(Be A Pro)カルチャーというものがありますよね。こちらはプレッシャーを乗り越える上で役立っていますか?
もちろんです。
ソラジマでは、社員が誰かに大きく刺激を与えるような素晴らしい行動をしたときに、Slackなどで「BAP!(Be a proの略プロだね!)」と称え合う光景が日常茶飯事です。
一人ひとりのナイスなアクションが取り上げられるので、とても刺激を受けます。
何かプレッシャーを感じているときでも、「あの人も同じようにプレッシャーを抱えながら成し遂げたんだ」と考えると、自分も頑張らなきゃって思えますね。
未経験からスタートしても成果を出せる編集者の共通点は何でしょうか。
共通点は、「熱量」と「こだわり抜く力」ですね。
未経験でも成果を出している人たちは、インプットとアウトプットの熱量が非常に高いと感じます。コンテンツ作りはもちろん、映画やドラマなどジャンル問わず物語を日々自分の中に取り込んでいる印象です。
熱量が高いが故に馬力があり、プレッシャーも跳ね除けているイメージがあります。
もう一つの「こだわり抜く力」とは?
コンテンツはブラッシュアップしようと思うと無限にできます。
今よりよい脚本、よいネーム、よい線画……と目指し始めたらキリがない世界です。その中で、どこまでこだわり抜けるかによって作品も変わってきます。
未経験でもヒットを出す編集の場合、その「こだわり抜く力」が突出しているんです。
一旦成果物が出来上がった後も、「ここの表情がおかしい」「このコマではもっとインパクトを与えたい」「カタルシスが足りない」など繊細な領域でこだわっています。
結果、そのこだわりが読者に届き、大きなヒットを生んでいます。
企画作りから脚本、ネーム、着彩など全工程において、クリエイターさんと一緒にどこまでこだわり抜けるかが、最終的な成果の差につながっている感覚はあります。
選考工程フロー図には「スキルに応じて複数の作品を担当する」とあります。時間管理の方法や優先順位の付け方を教えてください。
複数の作品を担当するときに一番意識しているのは、「即レスポンス」です。
クリエイターさんを待たせてしまうと、その間は作業が進められず報酬も発生しません。だから、成果物が届いたら、可能な限りすぐに確認して返信するようにしています。
また、複数作品を担当する編集者が一番つらい状況は、タスクが溜まってどこから手をつけていいか分からなくなり、結果的にクリエイターさんに負担をかけてしまっている時です。即レスポンスを心掛けることで、タスクが溜まってしまうこともなるべく回避するようにしています。
ただ、重めのタスクが同時に発生することもあります。
そんなときは、企画ごとの状況に応じて優先順位をつけます。例えば、リリースまで時間がない企画なら最優先ですし、長くクリエイターさんをお待たせしている企画なら早めに対応します。
編集者としての喜び、そして次の挑戦へ

この仕事で得られる一番のやりがいは何ですか?
クリエイターさんと一緒に頑張って作ってきた作品が世に出て、それが読者様に受け入れられた瞬間に大きなやりがいを感じますね。
本当に誰もがハッピーな瞬間というか、読者様が喜んでくれたら作り手の僕たちも嬉しいし、クリエイターさんにも報酬として還元できるので。
あとは、普段からクリエイターさんたちと一緒にネームや脚本、線画を作るというすべての工程が楽しいので、それがそのままやりがいになっています。
今後、編集者としてどんな作品や企画に挑戦したいですか?
先ほどのお話と少し被りますが、今の市場できちんとヒットしつつ、Webtoonを普段読んでいない人にも広く受け入れられ、多くの人に「夢中」を届けられる作品を作りたいです。
僕の周りでも「Webtoonを読んだことがない」という人はたくさんいて、ヨコ読み漫画より認知が低いと感じています。
一部、突出して認知されている作品もありますが、漫画として全体を見ると広く知られている作品はまだ少ないです。
今、Webtoonは過渡期に入っていて、ここから広く受け入れられる作品がどれだけ出てくるかによって市場の未来は変わってくるのではと考えています。
ソラジマやクリエイターさんたちに還元したいという想いもありますが、とにかくWebtoonで世の中に広く知れ渡るような大ヒット作品を作ることが目標です。

おわりに
ソラジマの編集者の仕事は幅広く、裁量が非常に大きいことが分かりました。
もちろんその分プレッシャーもありますが、仕事への情熱とソラジマならではのカルチャーによって乗り越えているようです。
さらに、未経験であっても漫画への強い熱意があれば、大きく活躍できることも分かりました。
編集者という仕事の奥深さとやりがいを感じつつ、挑戦できる環境が整っていることが、ソラジマの大きな魅力です。
漫画編集者を目指している方、Webtoonの制作に関わりたい方は、ぜひソラジマの採用情報をチェックしてください。
私たちと一緒に、今世紀を代表するコンテンツを創りましょう。
▶︎▶︎▶︎ 編集者の採用情報はこちら ◀︎◀︎◀︎
▶︎▶︎▶︎ クリエイター職の採用情報はこちら ◀︎◀︎◀︎
▶︎▶︎▶︎ 各種選考基準はこちら ◀︎◀︎◀︎